|
・長崎県のサッカーファミリー(医療関係者)紹介制度
[目 的]
トップレベルの選手だけでなく、長崎県内のあらゆるサッカー選手に対して、良質な医療を提供するために、サッカーに関わる(サッカーファミリー)医療関係者を紹介することを目的とする。
※この制度は平成25年1月、全国医学委員長会議で決定され、体制が整った県から順次実施することになっている。
[選 出]
1.各FAの医学委員会が選出する。
2. 選出の条件は、「JFA/47FA医学委員会の活動に参加、協力している人」
*例えば、講演会の講師、トレセン等のメディカルチェック、大会ドクター等
*チームドクター経験者、JFAサッカードクターセミナー、JFA“ATセミナー参加歴、JOC公認スポーツドクター資格等を参考にし、各FAの判断に任せる。
【医師】
<選考基準>
①
何らかの形(大会ドクター、講演会講師、メディカルチェックなど)で長崎県サッカー協会の活動に関与されている。
【理学療法士】
<選考基準>
①何らかの形(大会スタッフ、講演会講師、メディカルチェックなど)で長崎県サッカー協会の活動に関与されている。
②所属機関の医師の理解がある。
③所属機関で診療行為ができない場合には、選手・指導者の相談に乗り、適切な医療機関の紹介ができる。
<サッカーファミリー(医療関係者)名簿>
「医師」
|
|
氏名
|
専門領域
|
勤務先
|
|
長崎
|
西本 勝太郎
|
皮膚科
|
掖済会長崎病院
(095-824-0610)
長崎市樺島町5-16
|
|
今村 宏太郎
|
整形外科
|
いまむら整形外科医院
(095-856-2880)
長崎市葉山1-28-1
|
|
真崎 宏則
|
内科・呼吸器科
|
まさき内科呼吸器クリニック
(095-801-5908)
長崎市銅座町5−7 サイノオ医療ビル 3F
|
|
宮本 力
|
整形外科
|
長崎大学病院整形外科
(095-819-7321)
長崎市坂本1−7−1
|
|
梶山 史郎
|
整形外科
|
長崎大学病院整形外科
(095-819-7321)
|
|
安武 亨
|
外科
|
長崎大学病院外科
(095-819-7159)
|
|
白濱 克彦
|
整形外科
|
しらはま整形外科クリニック
(095-848-1986)
長崎市けやき台町1−12
|
|
宮村 庸剛
|
産婦人科
|
産婦人科 宮村医院
(095-845-0101)
長崎市橋口町22−10
|
|
田中 靖彦
|
歯科
|
タナカデンタルクリニック
(095-824-3281)
長崎市古川町6−35
|
|
|
|
|
|
|
県央
|
貞松 俊弘
秋山 寛治
川原 俊夫
|
整形外科
|
貞松病院
(0957-54-1161)
大村市東本町537
|
|
小無田 要
|
整形外科
|
コムタ外科・整形外科医院
(0957-22-2597)
諫早市幸町25−7
|
|
高原 晶
|
内科・循環器科
|
高原内科循環器科医院
(0957-22-1740)
諫早市小船越町1144−8
|
|
|
|
|
|
|
県北
|
富村 健
|
整形外科
|
富村整形外科医院
(0956-47-6840)
佐世保市相浦町256
|
|
増田 賢一
|
整形外科
|
増田整形外科医院
(0956-24-0056)
佐世保市高砂町4−5
|
|
田中 寿典
|
整形外科
|
田中医院
(0959-32-0033)
西海市西海町黒口郷1491
|
|
|
|
|
|
|
島原
|
稲田 善久
|
整形外科
|
稲田整形外科医院
(0957-62-6355)
島原市片町655
|
|
|
|
|
「理学療法士」
|
|
氏名
|
所属
|
|
長崎
|
岡 誠一
|
長崎医療技術専門学校
095-827-8868
長崎市愛宕1丁目36−59
|
|
早川 真史
東 知史
佐藤 潤
|
乗松整形外科医院
095-843-5161
長崎市平和町4−27 乗松ビル
|
|
高木 洋平
小森 峻
|
こんどう整形外科医院
095-850-6355
長崎市京泊町3-30-11
|
|
吉田 大佑
|
いまむら整形外科医院
095-856-2880
長崎市葉山1-28-1
|
|
|
|
|
|
県央
|
上川 哲朗
|
貞松病院
0957-54-1161
大村市東本町537
|
|
|
|
|
|
佐世保
|
持永 至人
|
増田整形外科医院
0956-24-0056
佐世保市高砂町4−5
|
|
|
|
|
|
島原
|
松本 伸一
嵜本 光洋
和田 卓也
井澤 康之
|
愛野記念病院
0957-36-0015
雲仙市愛野町甲3838−1
|
|
岡 健太郎
|
松岡病院
0957-62-2526
島原市江戸丁1919
|
・サッカードクターセミナーの報告
長崎大学整形外科 宮本力
日程:2012年3月17日(土)・18日(日)
場所:吉祥寺東急イン(1日目)、武蔵野公会堂(2日目)
<参加者> 富村 健(富村整形外科医院)
宮本 力(長崎大学整形外科)
梶山史郎(長崎大学整形外科)
滝田裕之(長崎医療センター研修医)
3月17日(土)から2日間の日程で、日本サッカー協会主催のサッカードクターセミナーに参加してきました。年2回開催の当セミナーも、今回で第50回ということもあり、以前よりもまして濃い内容だったようです。前ガンバ大阪の西野監督、元日本代表の宮本恒靖選手によるパネルディスカッションでは、「あるべきサッカードクター像」という題名で、様々な討論が行われました。西野監督とガンバ大阪のチームドクターとのやり取りが、吹っ切れた西野監督の毒舌もあり、かなり会場は盛り上がりました。「監督としてトレーナーは選べるが、ドクターは選べない。」と嘆いていたのが印象的でした。日本代表やJリーグのチームドクターによる「サッカードクターの現状と将来」のパネルディスカッションでは、Jリーグが開幕し海外から選手や監督がやってくるようになったため、サッカー選手だけでなく、“ドクター”も世界と比較されるようになってきていること、また、海外の選手はケガをしても日本の選手と比べあまり痛がらず、試合にでれば結果(得点)を出せるなど、Jリーグならではの実情も垣間見れました。このサッカードクターセミナーですが、4回以上受講することで各世代の代表チームに帯同する権利が得られるようです。長崎のサッカードクターの経験値を上げるためにも、ドクターの皆さん、コツコツ参加していきましょう。
以下に、セミナーで気づいた点を列挙していますので参照ください。
<要旨>
・突然死を防ぐため、メディカルチェックであるPCMA
(Pre-Competition Medical Assessment)が重要視されています。
・Jリーグトレーナーの資格別の内訳の紹介がありました。38チーム180人(非常勤含む)のうち111人が鍼灸師で最も多く、あ・マ・指師78人、柔整31人、PT 27人、AT 61人でした。重複したデータのようですが、思ったよりPTの数が少なく、スポーツトレーナーという職業にPTが介入しづらい現状が表れているような気がしました。
・感染症対策として、Jリーグ選手に対し、肝A、肝B、麻疹、破傷風の予防接種の義務化が、2013年シーズンより開始されます。
・脳震盪対策として、日本サッカー協会のメディカルコーナーの中にある、メディカル通信「第7回 サッカーで脳震盪?」に、脳震盪の対処法が掲載されていますので参照ください。
・アンチ・ドーピング部会報告では、低比重の取り扱いで適切な比重となるまで採尿することが必要となり、回数が1回とはかぎらないこと、クレンブテロール(S1 蛋白同化薬)の食物汚染による問題で、中国およびメキシコでは「競技会主催団体または国際競技連盟が指定するレストランで食事を摂ること」とのこと、治療量の吸入ホルモテロール(シンビコート)の禁止解除などの報告がありました。
・ドーピング事例として、レスリング男子日本代表選手が海外サプリ服用し大会出場停止、ラグビー男子日本代表選手が口ひげ育毛剤で2年間出場停止、重量挙げ女子が花粉症の薬(副腎皮質ホルモン含有)で優勝取り消しなどの報告がありました。
・Jリーグ19年間の外傷調査結果(約6000名)では、GKとDFでは頭頸部が多く、FWでは足関節が多いこと、ACL断裂は177件(試合中54%、練習中46%)、Jones骨折は167件(試合中21%、練習中79%)であったことが報告されていました。日本ではJones骨折の発生率が、欧米より10倍多いとのことで、その予防が重要課題となっているようです。
・高校サッカーのメディカルサポートが、学校の先生の管轄で、数が多く、基本的にアンケート調査(必要により精査)であり、これまで十分でないことが報告されていました。
・平成23年度U12 長崎県トレセンメディカルチェック結果報告書
実施日:平成24年2月18日(土) 15:00~17:00
場所:雲仙市みずほすこやかランド
対象者:U-12長崎県トレセン選手 43名
<チェック項目&担当者>
①
問診:今村(いまむら整形外科医院 医師)、村田(長崎百合野病院 理学療法士)
②
傷害チェック:上川(貞松病院 理学療法士)、小森(こんどう整形外科医院 理学療法士)
③
柔軟性チェック:田邊(いまむら整形外科医院 理学療法士)
和田(愛野記念病院 理学療法士)
岡(松岡病院 理学療法士)
④
フィールドテスト:吉田(いまむら整形外科医院 理学療法士)
<アンケート結果>
|
身長
|
平均151㎝(137㎝~172㎝)
|
|
1年間での身長の伸び
|
平均6.4㎝(2㎝~10㎝)
|
|
体重
|
平均39.3㎏(27㎏~66㎏)
|
①ポジションの内訳(複数選択可)
FW14名、MF14名、DF4名、GK6名
②利き足
右利き36名、左利き6名、両利き1名
③サッカーを始めた年齢

④サッカー以外のスポーツ経験(複数回答可)
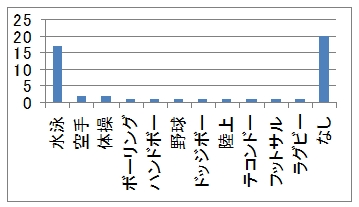
<練習状況について>
1週間の練習日数
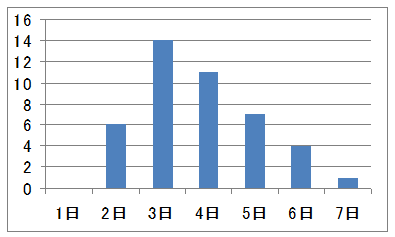
| 平日の平均練習時間 |
人数 |
| 1~2時間 |
4 |
| 2~3時間 |
34 |
| 3~4時間 |
4 |
| 4~5時間 |
1 |
| 土曜の平均練習時間 |
人数 |
| なし~1時間 |
3 |
| 1~2時間 |
1 |
| 2~3時間 |
8 |
| 3~4時間 |
14 |
| 4~5時間 |
4 |
| 5時間以上 |
5 |
| 未回答 |
8 |
| 日曜の平均練習時間 |
人数 |
| なし~1時間 |
7 |
| 1~2時間 |
1 |
| 2~3時間 |
8 |
| 3~4時間 |
5 |
| 4~5時間 |
2 |
| 5時間以上 |
7 |
| 未回答 |
13 |
| 1か月の平均試合数 |
人数 |
| 1試合 |
1 |
| 2試合 |
4 |
| 3試合 |
3 |
| 4試合 |
1 |
| 5試合 |
6 |
| 6試合 |
7 |
| 7試合 |
0 |
| 8試合 |
3 |
| 9試合 |
2 |
| 10試合以上 |
15 |
| 未回答 |
2 |
<怪我について>
| 1週間以上休む怪我の経験 |
人数 |
| あり |
14 |
| なし |
28 |
| 未回答 |
1 |
怪我の内容(複数回答可)
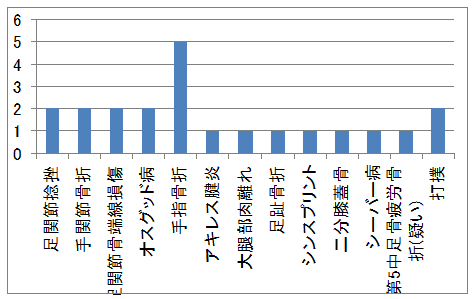
| オスグッド病について |
| 脛骨粗面に痛みを生じた経験の有無 |
人数 |
| ある |
14 |
| ない |
29 |
| オスグッド病と診断の有無 |
人数 |
| ある |
7 |
| ない |
36 |
| オスグッドの痛みで練習を休んだ経験 |
人数 |
| ある |
11 |
| ない |
3 |
| なぜ休んだか |
人数 |
| 自分・親の判断 |
7 |
| コーチの指示 |
3 |
| 医師の指示 |
3 |
| 未回答 |
1 |
| 腰痛について |
| 腰痛の経験の有無 |
人数 |
| ある |
6 |
| ない |
37 |
| 腰痛で練習を休んだ経験の有無 |
人数 |
| ある |
3 |
| ない |
3 |
| 腰痛で病院受診した経験の有無 |
人数 |
| ある |
3 |
| ない |
3 |
<まとめ>
今回、U-12長崎県トレセン選手のメディカルチェックを実施した。今回チェックをした選手の中に内科的に問題のある疾患を有する選手は見つからなかった。また、整形外科疾患ではオスグッド病の痛みを経験したことのある選手が全体の33%も占めていた。これは昨年のメディカルチェックの結果と同様の結果であり、オスグッド病の痛みが小学生サッカー選手のパフォーマンスに悪影響を与える原因の一つであることを再認識した。オスグッド病の発症要因の一つとして下肢の筋肉の柔軟性の低下が挙げられるが、今回の柔軟性チェック結果からはチェックを受けた選手全員に柔軟性の低下がみられた。今後、身長が伸びていくにつれてさらに柔軟性が低下し、怪我のリスクも高くなることが予測されるので、選手たちはサッカーのプレーに関することだけでなく、日頃のストレッチ方法や怪我に対する対応法など基本的なことを学ぶことも大切だと感じた。
・第8回トレーナー講習会(講演要旨):平成23年1月27日
「トレーニング理論」
講師 :岡 誠一(長崎医療技術専門学校 理学療法科)
目次
•
エネルギー供給系
•
筋収縮様式と筋肥大メカニズム
•
超回復
•
トレーニングの原則
•
ピリオダイゼーション
•
トレーニングカテゴリー
•
プログラム立案の流れ
1.エネルギー供給系
無酸素系代謝経路
・フォスファゲン系
(ATP-PCr系)
・早い解糖系
有酸素系代謝経路
・遅い解糖系
(有酸素系)
2.筋線維の種類
※TypeⅠ線維は有酸素的な能力に優れ毛細血管密度、ミトコンドリア密度、ミオグロビン含有量が高く、無酸素性の能力に劣るため収縮速度が遅いが疲労しにくい(赤筋)
TypeⅡ線維はATP分解酵素の能力に優れ収縮速度は早いが疲労しやすい(白筋)
3.等尺性収縮の特徴
メリット:
①器具がなくてもトレーニングできる。
②場所を選ばない。
③短時間にできる。
④疲労が蓄積しにくい
⑤ウエイトトレーニングにおけるスティック
ポイント(一番きつく感じるポイント)を重点的
に強化できる。
⑥十分に関節を動かせない時のリハビリテーション
に効果的である。
⑦初心者や中・高齢者にも安全に実施できる。
デメリット:
①スポーツ活動の動きに適していない。
②運動が単調である。
③トレーニング効果がわかりにくい。
④一定の関節角度しか強化できない。
⑤筋収縮の継続時間が長くなりがちである。
⑥自らの意志によって負荷が変化してしまい、
最大筋力発揮であっても筋への負荷が一定
にならない。
4.等張性収縮の特徴
メリット:
①動きを伴うため、スポーツ種目に応じたトレーニングを実施できる。
②重量・回数・頻度などを変化させることで目的に応じた効果を得ることができる。
③重量の変化により、効果がわかりやすい。
デメリット:
①器具・設備が必要である。
②フォームの習得が難しいものがある。
③高重量を行う場合、事故・障害の危険性を伴う。
5.初動負荷と終動負荷
初動負荷:動きの始めに一番負荷がかかる運動
(例:ダンベル等)
終動負荷:動きの最後に一番負荷がかかる運動
(例:ゴムチューブなど)
6.筋肥大のメカニズム
7.超回復
トレーニングのような刺激を身体に与えると一時的に疲労し、体力水準は低下するが、適切な休息をとることにより、以前の水準よりも回復する。
超回復の段階
第1段階:トレーニングによる疲労により、身体諸機能が低下する。
第2段階:休息により、枯渇したエネルギーの回復や損傷した筋線維の修復
が行われる。
第3段階:適切な休息により以前の水準よりも回復する。(超回復)
第4段階:超回復の効果が持続している期間内に再度刺激が与えられなけれ
ば効果は消失し、日常生活レベルに適応した機能水準に戻る。
超回復が起こるための回復期間
トレーニングにより疲労した身体が回復する期間は一般に24時間とされている。
有酸素系トレーニング・・・6~8時間
パワー系トレーニング・・・24~72時間
※トレーニング内容や個人差もあり、実際の個々の正確な長回復に必要な休息時間を把握するのは難しい。
※高負荷と低負荷を組み合わせたプログラムによってトレーニング頻度を落とすことなくパフォーマンスを向上できる。
8.トレーニングの原則
•
特異性の原則(SAIDの原則)
•
過負荷の原則(オーバーロードの原則)
•
斬進性の原則
•
意識性の原則
•
全面性の原則
•
個別性の原則
•
反復性の原則(継続性の原則)
意識性(自覚性)の原則
・トレーニング効果を効果的に獲得するためには、目的や方法を十分に理解して実施しなければならない。
・指導者はもちろん、競技者も与えられたプログラムの意義をしっかり理解して行う。そのためには競技者に対し、事前の説明とディスカッションを十分に行う必要がある。
最低限、選手に理解してほしいこと
□どの能力を強化しているのか
□その能力の強化により、専門競技の何に役立つのか
□時期によるプログラムの変化(ピリオダイゼーション)は何のために行っているのか、また今はどの時期なのか。
全面性の原則
•
トレーニングは部位や種目に偏ったものではなく、バランスよく強化しなければならない。
•
特にジュニア選手に関しては長期的なトレーニングプログラムには、身体能力の基礎となる能力の全面的な発達が欠かせない。
•
全面的な能力を開発しておくことで、将来より高度なテクニックを習得する際にも比較的早く習得できる。
個別性の原則
•
トレーニングは年齢・性差・体格・体力・競技レベル・経験・健康状態・個人の精神的特性などを考慮し、個々の状態に応じたプログラムを作成しなければならない。
スキャモンの発育曲線
脳神経系の発育は早く、8歳くらいの学童期にはほぼ完成に近づき、12,3歳
で成人の水準に達する。一方、生殖系は成長、発育が遅く、18~20歳で完成される。一般的な器官系は10歳くらいから完成に近づく。筋肉は15歳で成人の33%、16歳で44%くらいといわれる。したがって、筋力トレーニングは13~14歳から始めるのがよい。しかし、成長を司る骨端線は16~17歳ごろ閉鎖するので、強力な筋活動はそれ以降がよい。また、持久力を支える循環機能は25歳ごろ、呼吸機能は18歳ごろにピークが見られる。
年齢別の特徴
(5~8歳)
•
主に神経系の発達が著しい。
•
プレゴールデンエイジと呼ばれる。
•
専門的なトレーニングよりも遊びの中で投げる・走る・跳ぶなどの動きをとりいれた運動を行うのが望ましい。
•
次の専門的なトレーニングの基礎となる。
(9~12歳)
•
この時期には神経系の発達が成人のレベルまで達し、形態の発育も安定している。
•
ゴールデンエイジと呼ばれる。
•
さまざまなスキルをすぐに体で覚えることができる。
•
専門競技の基礎的な動作習熟には適した時期であるといえる。
(13~16歳)
•
12歳以降、発育のスパートを迎える。
•
骨の発育に筋の柔軟性が追いつかず、筋の付着部に痛みを引き起こすいわゆる成長痛という症状も出現する。
•
精神的にも不安定な時期となる。
•
呼吸循環系の能力が向上する時期であるので、持久的なトレーニングを実施することが望ましい。
(17~20歳)
•
生殖器系の発育が急激となり、男性ホルモンの分泌も盛んとなる。
•
骨格筋の発達も著しいため積極的な筋力トレーニングやパワー系のトレーニングを取り入れていく時期である。
少年期の留意点
① 基礎体力の養成と技術練習を並行してやらせるとよい
② 障害発生はクラブ活動などを開始した1~2ヶ月後や、中学、高校への入学当初に頻発する傾向がある
③
発育には個人差があり、過度な運動、偏側性のある運動は骨関節の成長を阻害
することがある
④ 子供は決して成人のミニチュアではない(骨・筋はまだ成長途中である。)
継続性(反復性・可逆性)の原則
トレーニングは一時的に行うのではなく、計画的に継続・実施しなければならない。
9.ピリオダイゼーション
目的とするトレーニング効果を獲得するために、トレーニング計画を目的別に「期分け」し、各期に応じてトレーニング量・強度・種類を変化させること
マクロサイクル
メゾサイクル
ミクロサイクル
トレーニング周期における目的
|
トレーニング周期
|
準備期
(前半)
|
準備期
(後半)
|
試合期
|
移行期
|
|
目 的
|
一般的
トレーニング
|
専門的
トレーニング
|
専門的能力の完成
|
積極的疲労回復
|
※特に準備期の前半は基礎体力増強のためのトレーニングを目的とし、準備期後半では専門種目に特異なトレーニングを目的とする。
試合期では体力・技術の両側面から専門的能力の完成を目指す。
レジスタンストレーニング
負荷・抵抗をかけるトレーニング全般を指す
ウエイトトレーニング・ストレングストレーニング・筋力トレーニングなどがこれにあたる。
スピード・パワー系トレーニング
•
プライオメトリックトレーニング
→瞬時に最大筋力を発揮するパワー養成トレーニング
•
アジリティートレーニング
→瞬時の方向転換、ストップ、ダッシュに関わるトレーニング
有酸素運動のトレーニングタイプ
|
トレーニング
タイプ
|
週当たりの頻度
|
時間(トレーニング部分)
|
強度
|
|
LSD
|
1~2
|
レースの距離もしくはそれ以上
|
70%VO2max以下
|
|
ペース・テンポ
|
1~2
|
20~30分以下
|
乳酸性作業閾値、
レースでのペースを少し上回る
|
|
インターバル
|
1~2
|
3~5分(運動-休止比は1:1)
|
VO2max付近
|
|
レペティション
|
1
|
30~90秒(運動-休止比は1:5)
|
VO2max以上
|
|
ファルトレク
|
1
|
|
|
10.プログラム立案の流れ
ニーズの分析
・スポーツ特性の分析
・競技者の分析
・健康診断
・体力測定 など
トレーニング種目の選択
・エクササイズのタイプ
・競技特異性
・エクササイズの経験
・利用できる機器・環境 など
トレーニングの頻度
・ピリオダイゼーション
トレーニングの順序
・実施順序
・実施方法
トレーニングの負荷と回数
・目的に応じた負荷と回数の設定
休息時間
・エクササイズ間の休息の設定
ニーズ分析(スポーツ特性の分析)
1)動作分析
□記録系、採点競技系、球技系、格技系のうちどの競技に分類されるか。
□どのような順序で運動連鎖が行われているか。
□主にどのような肢位で力発揮が要求されるのか。
□どの筋がどの肢位で要求されるのか。
2)生理学的分析
□筋肥大、筋力、パワー、持久力のうちどの能力が最も重要か。
3)スポーツ医学的分析
□どの部位がオーバーユースになりやすいか。
□傷害部位を防ぐのに役立つ動作はどのようなものか。
ニーズ分析(競技者の分析)
1)身体特性の把握
□現状の体格や形態が競技において一般的に有利か不利
□骨格のアライメントに異常はないか
□傷害歴、疼痛の出やすい部位はないか
□競技を継続する上で重要な疾患はないか
2)トレーニングレベルの把握
□これまでどのようなトレーニング指導を受けてきたか。
□どれくらいの期間トレーニングを実施してきたか。
□エクササイズテクニックの習熟度はどの程度か。
□トレーニングに関してどの程度の知識を持っているか。
□どの程度のレベルで競技してきたか。
3)体力レベルの評価
□身体組成、四肢周径、筋力、柔軟性、パワー、スピード、筋持久力、持久力などを評価する。その競技特有の動作を取り入れた測定を実施してもよい。
□上記項目の結果が、トップ競技者と比較してどの程度なのか、またチームの中でどのレベルなのか。
4)目標設定
□1)~3)を客観的に分析し、長期的なプログラムから獲得する目標をどのレベルに設定するか。
□各シーズンでどの能力を向上させることを第一優先とするか。
トレーニング種目の選択
トレーニング計画は、数多くのトレーニング種目特性と効果を把握した上で選択しなければならない。
コアエクササイズ:競技に直接の影響力を与える筋群の強化 <最重要>
→大筋群を利用した多関節運動
補助エクササイズ:競技に直接的な影響力の少ない運動
→小筋群を利用した単関節運動
エクササイズの選択(注意点)
1)エクササイズの種類
□コアエクササイズか、補助エクササイズか
□直接的なパフォーマンスの向上か、リハビリテーションや傷害予防のためのエクササイズか
2)競技特性
□その競技に必要な筋群を強化するエクササイズを選択する
□競技の動作、及びスピードを考慮する
□主動作筋と拮抗筋のバランスを考慮する
3)エクササイズの経験
□特に高重量を扱うフリーウエイトエクササイズの経験があるかどうか
□フォームの崩れ
トレーニングの頻度
・一般に1週間における実施回数をいう。
・週3回のレジスタンストレーニングが推奨される。
・少なくとも1週間に1日は休息を設ける。
・体の強化部位を分割し、プログラムを組むことで週6日のトレーニング実施をすることも可能(スプリットルーティン法)
・頻度は試合や技術練習の割合によって変化させる。
・トレーニング強度も依存する。
高強度のセッションを実施した後は休息を長くとるなど。
・上肢と下肢では上肢の疲労回復のほうが早いとの報告がある。
トレーニングの順序
※強度の強いもの、集中力の必要なもの、エネルギーが必要なものなど身体的・精神的負荷の強いものから弱いものへ実施する(プライオリティーの原則)
□パワートレーニング⇒コアトレーニング⇒補助トレーニング
□大筋群⇒小筋群
□複合関節運動⇒単関節運動
□高エネルギー運動(瞬発系)⇒低エネルギー運動(持久系)
□上肢⇔下肢(交互に行う)
トレーニング法
・プレエグゾーション法(予備疲労法)
特定の筋を単関節運動により、事前に疲労させ、その後複合運動を実施することで筋に大きな負荷を与える方法
例)レッグエクステンション⇒スクワット
トライセプスエクステンション⇒ベンチプレスなど
・スーパーセット法
主動作筋と拮抗筋を交互に行う。短期間で目的とするトレーニングセッションを終了できるが、精神的な持続を要求するため、上級者向けの方法である。
例)バイセプスカール⇔トライセプスプッシュダウン
レッグエクステンション⇔レッグカール など
・コンパウンドセット法
主動作筋と共働筋を刺激する方法。同じ筋群を刺激する2種類のエクササイズを連続して行い、これを1セットとする。
短時間の間に特定の筋に対して効率よく刺激を加えることができるが、精神的な持続を伴うために、上級者向けの方法である。
例)バイセプスカール⇒ハンマーカール
(上腕二頭筋) (腕橈骨筋)
レッグエクステンション⇒ヒップフレクション
(大腿四頭筋) (大腿直筋、腸腰筋)
トレーニング量
1回のトレーニングの中で実施された重量の総量をさす
例)50kgの重量で10回×3セット実施した場合のトレーニング量は
50kg×10回×3セット=1500㎏
となる。
(例)ベンチプレス1RMが100kgの選手の場合
◇筋肥大(オフシーズン)
70kg×12回×6セット=5040㎏
◇筋力向上(プレシーズン前半)
85kg× 6回×6セット=3060㎏
◇パワー向上(プレ後半~インシーズン)
95kg×2回×3セット=570㎏
※インシーズンに向けて挙上重量は増加するが、トレーニング量は減少する
ため、筋への負担は軽くなりつつ、力発揮は大きくなるようなプログラム
とする
・平成22年度中学生サッカー選手に関する傷害調査報告書
【はじめに】
長崎県サッカー協会スポーツ医学委員会では、平成20年度に高校生年代の外傷・障害の発生状況を把握する目的でアンケート調査を実施した(巻末)。その結果、全体の約60%の選手がなんらかの傷害で1週間以上プレーできない経験を持ち、その多くが傷害のために現在でもプレーに悪影響があると回答していた。それを踏まえて中学生年代でも外傷・障害の発生状況も把握する必要があると考え、中学生を対象としたアンケート調査を行った。特に、中学生年代では腰痛の発生が増加し、長期間のプレー中止を余儀なくされることも多いことから、腰痛に注目して調査した。
【調査の概要】
1.
調査期間:平成22年7月~8月末
2.
対象
長崎県サッカー協会登録の第3種の選手(中学1~3年生)
長崎地区36チーム(1046名)、西彼地区10チーム(259名):計1305名(平成22年4月現在)
3.
回答率:29チーム(63%) 565名(43.3%)
【調査結果】
1.
学年
|
中1
|
中2
|
中3
|
記載なし
|
|
208名(36.8%)
|
226名(40%)
|
116名(20.5%)
|
15名(2.7%)
|
2.性別
|
男子
|
女子
|
記載なし
|
|
547名(96.9%)
|
4名(0.7%)
|
14名(2.4%)
|
3.利き手・利き足
1)利き手
|
右利き
|
左利き
|
両利き
|
記載なし
|
|
497名(88%)
|
50名(8.8%)
|
0名
|
18名(3.2%)
|
2)利き足
|
右利き
|
左利き
|
両利き
|
記載なし
|
|
489名(86.5%)
|
47名(8.3%)
|
10名(1.8%)
|
19名(3.4%)
|
4.ポジション
|
FW
|
95名
|
|
MF
|
165名
|
|
DF
|
166名
|
|
GK
|
47名
|
|
決まっていない
|
92名
|
5.サッカーの開始年齢について
中学1年が一番多く(132人)、ついで小3(122人)、小2(105人)の順で、こららの学年で全体の約7割を占めた
6.小学生当時および現在の練習日数・時間
|
|
練習日数(1週間平均)
|
練習時間(1日平均)
|
|
小学生
|
3.9日(1日~7日)
|
2.4時間(1時間~6時間)
|
|
中学生
|
6.0日(1日~7日)
|
2.8時間(1時間~6時間)
|
7.サッカー以外のスポーツ歴について(複数回答可)
サッカー以外のスポーツ歴の有無については、「ある」と答えた選手は258名(45.7%)、
「ない」と答えた選手は307名(54.3%)であった。
「ある」と回答した選手の競技種目
水泳が184人と圧倒的に多く、残りは空手・バスケットボール・ソフトボールが20人前後であった
8.「これまでにサッカーによって1週間以上練習または試合を休む必要があった傷害」に関して
1)傷害の有無
全体の約5割の選手が何らかの傷害で
1週間以上練習・試合休止の経験をしていた。
2)「ある」と答えた選手の受傷部位(複数回答可)
部位別では、足関節(20.1%)が最も多く、次いで、膝関節(17.6%)、手・指(14.7%)、足部(13.8%)、
腰部(8.3%)の順に多かった。また、下肢が全体の約70%を占めていた。
9.腰痛に関する質問
1)今までに腰痛が1週間以上続いた経験の有無に関して
2)初めて腰が痛くなった年齢
中2の33人が一番多く、次いで中1の29人と中1中2で6割以上を占めた。
3)腰の痛みによる病院受診の有無
|
ある
|
ない
|
記載なし
|
|
79名(14%)
|
484名(85.7%)
|
2名(0.3%)
|
4)現在の腰痛の有無
|
ある
|
ない
|
記載なし
|
|
41名(7.3%)
|
517名(91.5%)
|
7名(1.2%)
|
現在、腰痛が「ある」と答えた選手(41名)の腰痛継続期間
| 1週間以内が13人と一番多く、次いで1週間から1ヶ月が9人であり、1ヶ月以内で全体の5割強を占めた。 |
|
|
現在、腰痛が「ある」と答えた選手(41名)の腰痛誘発動作
| 腰痛誘発動作で一番多かったのは前屈、ついで体をそった時で、長時間の座位も三番目に多かった。 |
|
|
5)①腰椎分離症(腰椎疲労骨折)の診断の有無
|
あり
|
なし
|
記載なし
|
|
18名(3.2%)
|
542名(95.9%)
|
5名(0.9%)
|
特に、1週間以上腰痛が継続したことのある選手100名については、腰椎分離症(腰椎疲労骨折)の診断を受けたことのある選手の占める割合は18名(18%)であった。
② 診断された年齢
中1,中2で過半数を占めた。
【まとめ】
今回の調査の結果、約50%の選手が何らかの傷害によって1週間以上のプレーの中止を経験していることが分かった。これは高校生のアンケート調査の結果(約60%)と比較して大差ない結果であり、すでに中学生の時点でこれだけ多くの選手が重大な傷害を経験していた。また、受傷部位に関しても高校生年代の調査と同様に足関節、膝関節などの下肢の傷害が多く発生しており、年代が変わってもサッカーでは下肢の傷害が多いということが再認識された。今回のアンケート調査を実施するに当たり腰痛、特に腰椎分離症に注目した。高校生年代での調査では腰部疾患全体に占める分離症の割合は約38%であったが、今回の中学生の調査では18%と約半数であった。したがって、中学後半から高校前半にかけて腰椎分離症が発生していることが推察された。また、高校生の調査で腰椎分離症106名中47名(44.3%)は「現在でもプレーに影響がある」と回答していた。今回の調査では、腰椎分離症のあったものはすべて1週間以上腰痛が継続しており、腰痛が持続し痛みが軽快しない選手はすみやかに医療機関を受診し適切な診断・治療を受ける必要がある。今後、腰痛のため十分にプレーができないという選手が少しでも減るように注意していく必要がある。
一般的な腰痛の原因には身体の柔軟性の低下、体幹筋力の低下などが挙げられる。身長が大きく伸びる中学生年代では、身体の柔軟性が低下しやすく、さらにその成長に見合った体幹の筋力が備わっていないことが多い。そのため、中学生年代では特に、柔軟性低下を防ぐための十分なストレッチや、体幹筋の筋力トレーニングが重要である。スポーツ医学委員会では、今年10月に行われた全国高校サッカー選手権大会長崎県大会の組み合わせ抽選会後に、高体連からの依頼で腰痛に関する講演と腰痛予防のためのストレッチ・体幹筋のトレーニング法の実技指導を行った。今回の調査の結果から中学生年代でも、こういった活動が必要であると痛感した。
近年、JFAでもカテゴリーごとにメディカルサポートを充実するような動きが活発化している。長崎県でも第1種から第4種までの各カテゴリーにおいて会場ドクターや理学療法士の派遣、国体へのトレーナーの派遣、トレーナーの育成、選手への応急処置・ストレッチ・トレーニングの指導講習会などの様々な活動を行っているが、今後もさらにメディカルサポート活動に力を入れ、選手がよりよい状態でプレーできるよう支援していきたいと考えている。
長崎県サッカー協会スポーツ医学委員会
・第6回トレーナー講習会(講演要旨):平成22年9月15日
「テーピングの理論と実技」
講師 :有川 康弘(アスレティックトレーナー 大久保病院)
(総論)
1. テーピングとは?
解剖学的な構造および外傷・障害の発生機転(メカニズム)などにそって身体の一
部に粘着テープ、伸縮性粘着テープを規則正しく貼ったり、巻いたりする方法。
2. テーピングの目的
①外傷の予防、②応急処置、③再発予防
3. テーピングの効果
①関節の特定の動きを任意に制限する、②圧迫を加える、③痛みを和らげる、④精
神的な助けとなる
4. テーピングの有効性
①可動域、運動能力に及ぼす影響:足関節に関して、底背屈・内外反など20~30%
ほど可動性を制限したなどの報告あり、②持続性:10分間の運動で40%の支持力
低下という報告もあり、③臨床的効果:テーピングを行うことで捻挫の発生率が低
下したなどの報告あり、④関節覚・固有受容器に及ぼす影響:機能的不安定性を有
する者にテーピングを行うことで有意に向上させるという報告もあり。
5. テーピングにおける基本的注意
①正確な診断(外傷の種類・メカニズムの把握、外傷・障害の重症度・回復状態で
テーピングが実施できる時期などが異なってくるため確認しておくこと)、②腫れ
の有無、③循環障害・筋腱障害(巻く強さの加減、当該部位の筋腱を緊張させて巻
く)、④神経障害(橈骨・尺骨・腓骨神経など)、⑤適用時間(皮膚の影響やテーピ
ングのずれを考慮)、⑥テーピングの方法(外傷の回復状態、スポーツ種目、ポジ
ションなどに応じて方法、強度を変更)
6. テーピング用テープの種類と特性
幅:13 mm、19
mm、25 mm、38 mm、50 mm、75 mm、100 mm
長さ:4~4.5m、6.9
m、12 m、13.7 m
生布の材質:非伸縮テープ、伸縮テープ(ハンディカット:ソフト、ハード)
接着剤の組成:主に生ゴムを使用
テープの色:非伸縮(白色、ベージュ、青など)、伸縮(ベージュか、茶色、一部
白色)
特性:手で切る時は切りやすく、反対にテープ全体に張力が加わった時には切れに
くいもの、装着した際にごわごわとした感じがないものが良い。
テープの保管:①高温多湿の場所を避ける、②できる限りケースの中に入れ、テー
プの上に直に物などを載せて、変形させない。
・第5回トレーナー講習会(講演要旨):平成22年7月16日
「アンチ・ドーピングについて」
講師:小無田 要(コムタ外科・整形外科医院)
真崎 宏則(まさき内科呼吸器クリニック)
(総論)
1.ドーピングとは?
競技能力を高めるために薬物などを不正に使用すること
2.なぜいけないか?
①スポーツ固有の価値を損なう
②不誠実(アンフェア)
③社会悪である
④競技者自身の健康を害する
3.アンチ・ドーピング事業
WADA:世界ドーピング防止機構
JADA:日本ドーピング防止機構
4.ドーピングの判断基準は?
WADAより毎年出される禁止表に記載された禁止物質・禁止方法に準じる
5.禁止表の主要項目
1)常に禁止される物質と方法(競技会(時)及び競技会外 )
禁止物質 ・蛋白同化薬 :いわゆる筋肉増強剤
・ペプチドホルモン :血液を増やす薬など
・利尿薬隠蔽薬 :痛風の薬など
禁止方法 ・酸素運搬能の強化 :輸血など
・化学的・物理的操作:尿のすりかえ、 静脈注射など
・遺伝子ドーピング
2)競技会時に禁止対象となる物質と方法
1)に加えて 興奮剤、麻薬、糖質コルチコイド
3)特定競技において禁止される物質
競技会時に限りアルコール、ベータ遮断薬
4)監視プログラム
違反ではないが乱用されると今後禁止物質にはいる可能性のあるもの
カフェインなどの興奮剤、モルヒネなどの麻薬
6.ドーピング検査の実際
・競技者の尿、血液を採取しWADA認定試験所で分析
→日本は三菱化学メディエンスのみ
・競技会検査、競技会外検査がある
「競技会検査」での禁止対象
(1)常に禁止される物質と方法
(2)競技会検査で禁止される物質と方法
「競技会外検査」での禁止対象
(1)常に禁止される物質と方法のみ
・検査を受ける競技者は同伴者1名を伴うことができる
→皆さんがドーピングの知識をもっていれば同伴できます。
7.TUE(治療目的使用に係る除外措置)
治療のため禁止薬物を使用する必要があるときに申請する。
以下の条件を満たす必要あり
・治療上必要
・他に治療法がない
・使用しても競技力を高めない
一般的なTUE申請対象疾患
・気管支喘息→吸入内服ベータ2作用薬(気管支拡張薬)
・関節リウマチなど炎症性疾患→糖質コルチコイド
・糖尿病 →インスリン
(TUE変更点)
今年より吸入ベータ2作用薬のサルブタモール・サルメテロールに関してはTUE申請が不要になった。
8、ドーピング陽性が確定した場合
日本ドーピング防止規律パネルで審議され制裁措置がとられる。
使用物質、方法で制裁が異なる。
① 禁止物質・方法を使用した場合
1回目:2年間資格停止、2回目:永久資格停止
② 特定物質を使用した場合
特定物質とは禁止物質の中で医療用として一般的に使用されているもの
1回目:1年未満、2回目:2年間、3回目:永久資格停止
* ①②ともにドーピングが認められた競技以降の成績記録は抹消される。
(各論)
1、気管支喘息の薬
多くの喘息治療薬はドーピング対象になるためTUE申請が必要になることが多い
よってドーピングに詳しいスポーツドクターに相談してください。
*今年より吸入サルブタモール・サルメテロールに限りTUE申請が不要になった。
2、市販のかぜ薬、胃薬
うっかりドーピングの原因として一番多い。
かぜ薬にはエフェドリン・メチルエフェドリン・プソイドエフェドリンなどの禁止物質が入っていることが多い。
胃薬では禁止物質のホミカに注意。
例)かぜ薬
葛根湯、小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、浅田飴
パブロンN、エスタックイブ、パブロン鼻炎カプセルSなど
胃薬
イノセア消化薬、とくじんA錠、ホミカロート錠、ワクナガ胃腸薬Gなど
対策
通常量の服用ならば3日前までにやめればまず大丈夫。
*普段から安易に薬を服用しない習慣が大事!
3、漢方薬
副作用がなく安心な薬というのは間違い!
禁止物質を含むものが結構ある。同じ名前でも製造元・原料の産地・収穫時期などで成分が違うことがあるため成分が不確かである。よって安易に服用すべきでない。
例)葛根湯:(かっこんとう)、麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)
小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、麻黄湯(まおうとう)など
4、サプリメント
健康食品だから大丈夫というのは大きな間違い!
医薬品のように成分表示が信頼できない、また効き目を上げるためにステロイドを混ぜていることがある(特に外国製は要注意!)
大丈夫な補助食品はJADA認定商品マークがついているもの(JADAのHP参照)
5、名前が似た薬
名前が似ていても成分が異なることがあります。
例1)市販の総合感冒薬
「ストナアイビー」:OK
「ストナアイビー顆粒」:NO!→禁止物質のメチルエフェドリンを含む
例2)市販の胃腸薬
「ワクナガ胃腸薬U」:OK
「ワクナガ胃腸薬G」:NO!→禁止物質のホミカ含む
6、外用薬
ステロイドを含有する塗り薬は大丈夫か?
→通常の皮膚疾患に使用するならば大丈夫
点眼・点鼻・口内炎の薬は大丈夫か?
→通常使用ならば大丈夫
7、点滴、静脈注射
医学的に必要であればTUEなしに可。
8、トレーナーとして競技者に指導すべきこと
・治療に使った薬は記録に残すこと
①薬の説明書を保管する。
②国体選手必携書の「常備薬メモ欄」に病院の薬市販薬の正確な薬物名、用法、用量を書き込む。
③ 症状があるときだけ飲む薬は、飲んだときに日付と用量をメモする。
・薬で分からないことがある時どうするか
中身のわからない薬は絶対に飲まない!
①薬で不明な点はドーピングに詳しい主治医あるいはチームドクターに相談する。
②日体協ホームページで使用可能な薬を確認。
④ 薬剤師会アンチドーピング・ホットラインを利用。
9、最後に
・ドーピング対象の禁止物質、特定物質は毎年変わりますので古い資料で判断しないでください(本日の講習内容も来年は変更点がでてくるはずです)。
・禁止物質・方法などをすべて覚える必要はありません。何を調べどこに聞けばいいかを覚えておいてください。
(参考)
・最新の禁止物質・方法・大丈夫な補助食品などを調べるには
→JADAホームページ(http://www.anti-doping.or.jp/)
・薬について聞きたい場合、調べたい場合
→薬剤師会アンチドーピング・ホットライン(長崎:095-846-5918 )
受付時間:平日10時~12時、13時~16時
→日体協ホームページ(http://www.japan-sports.or.jp/)
・国体選手に帯同する場合
→国体選手必携書をみれば、ドーピングについて、使用可能な薬一覧
各県の薬剤師会アンチドーピング・ホットラインがわかります。
・第4回トレーナー講習会(講演要旨):平成22年5月14日
「日常生活で必要な皮膚病の知識」
講師:西本 勝太郎(長崎エキサイ会病院皮膚科)
皮膚の働きについてまず誰でも考えることは、外部から加えられる様々な障害から体を守るための器官ということです。われわれが出会うことの多い外からの傷害のいくつかについて、どのように対応したらよいのかをまとめます。
1)物理的な刺激・傷害——急性の外傷である、打撲・切創・裂創などは外科的な処置が必要ですので、これは別の機会にゆずります。慢性にくり返される外力による皮膚の変化の代表的なものが、「たこ、うおのめ」です。「たこ」と「うおのめ」は少し違うものですが、どちらにしてもその治療は、「出来ないようにする」ことです。一番大事なのは靴の選び方で、つま先にゆとりがあり、かかとに指1本が入るぐらいの大きさ、ひもでしっかり固定できる、ことが原則です。実際にはそれまでの習慣通りに窮屈な靴を選ぶ人が多く、しっかりと指導する必要があります。痛みをとめるために病変を削るのは、あくまで一時しのぎと考えてください。
2)化学的な刺激・傷害——つまり化学物質による皮膚炎、一般に「かぶれ(正式には接触皮膚炎)」といわれます。このなかには強い酸のように触れた人が誰でもかぶれるものと、「はぜまけ」や金属アレルギーのように、一部の人にだけごく薄い濃度で皮膚炎を起こす場合があります。いずれにしても原因をはっきりさせることが大切で、「かぶれ」の場合、皮膚の変化が起こっている場所と、日常生活のなかでそこに触れる可能性のあるものを突き合わせていくことで、ある程度見当がつきます。確認するための一番簡単な方法は、疑わしいものをそこに張り付けて1−2日おいてみることで、そこに皮膚炎が起こればそれが原因の一つと考えられます。「かぶれ」の患者さんで、その原因をはっきりさせずに軟膏による治療だけを行っていることがありますが、これは問題の解決ではなく、単に薬の副作用をまっているようなものです。「しっぷかぶれ」「化粧品かぶれ」など身近によくあるものですから、充分に注意してください。
近頃よく話題となるアトピー性皮膚炎にも同じような状況があります。アトピー性皮膚炎の原因としていろいろの記事を目に来ることが多いと思いますが、要は「弱い皮膚」と「皮膚への刺激」の組み合わせだと言うことです。アトピー性皮膚炎の場合、周囲からの刺激を充分にさけることと同時に、保湿剤などで弱い皮膚を守ることが大切です、近ごろの洗いすぎの風潮は、皮膚をいためる大きな原因となっています。
3)紫外線と皮膚−—紫外線による皮膚の障害も物理的な障害の一つですが、やや特殊なので別にまとめます。紫外線は太陽光に含まれる波長の短い光線で、日焼けの原因となるものです。最近紫外線の害が大きな話題となっています。紫外線を多く浴びることによって、皮膚の老化と、皮膚ガンになる頻度が高くなることが広く知られてきました。
われわれの健康な生活に必要な紫外線の量は、日常生活でとくに意識することなく浴びているぐらいで十分です。つまり紫外線はなるべくさけた方がよいと言うことです。われわれが一生の間に浴びる紫外線の大半は、すでに10代までに浴びてしまうとも言われています。とくに年少者で注意して欲しいことです。
a) 紫外線のピークは、一日の内では正午を中心とした数時間ですから、この時間の屋外活動はなるべくさける。
b) 戸外では紫外線への防御を十分に。帽子——十分につばの広いもの、長そでのシャツ、サングラス、日焼け止め(サンスクリーン)の利用。
c) 日焼け止めは, SPF 30以下、PA ++ 程度で十分。たっぷり塗ることと、数時間おきに塗り直すこと。顔、手以外に首の後ろを忘れずに。
などを注意してください。
皮膚病のなかには治せる(治療できる)皮膚病と、現在の医学では治せない皮膚病があります。しかしどちらも治療法はあります。皮膚を健康に保つと言うことは、全身を健康に保つことでもあるのです。
・第2回トレーナー講習会(講演要旨):平成22年1月27日
「四肢外傷」
講師:宮本 力(長崎大学医学部整形外科助教)
サッカーはコンタクトスポーツであり、打撲や捻挫、ときには骨折、靭帯損傷などが発生します。Jリーグに関するデータでは、1試合につき約1件の外傷が発生します。発生頻度で最も多いのは、足関節の捻挫です。しかし、「たかが足首の捻挫」と考え、正確な診断を怠ると、後で障害を残す恐れがあり注意が必要です。肉離れや靭帯損傷では重症度により、治療法や競技復帰が異なります。重症度を医療機関で判定する必要があり、重症の場合には、選手に対して治療期間の必要性を十分に教育することも大事になってきます。出血を伴うケガが発生した場合には、必ず手袋を着用し、驚いたり動揺せず、冷静に対処する必要があります。
サッカーの試合中に、選手が負傷した場合のメディカルスタッフの対応について、少し説明します。テレビのサッカー中継などで、見たことがあると思いますが、選手が試合中に負傷すると、主審の指示で、最大2名までのトレーナーもしくはドクターが、ピッチの中へ入ることができます。サッカーでは、ピッチの中で治療してはいけないというルール(例外①ゴールキーパーの負傷②重篤な外傷)がありますので、一旦選手をピッチの外へ、徒歩もしくは担架で出す必要があります。その間チームは、1人少ない不利な状況で戦うことになりますので、短時間で選手をチェックしなければなりません。まず、選手がどこを痛めたかを確認し、プレーできるかどうかを質問します。「できない」と選手が答えるようであれば、プレーできないことをベンチへ伝達します。選手が「できる」と返答した場合は、ケガの状態を評価しなければなりません。この際、各部位の外傷について、ある程度知識が必要になります。実際には、疼痛部位や圧痛部位を確認し、腫れの具合、変形の有無をチェックします。軽傷と思われれば、その場で足踏みなど簡単な動作を行わせ、問題がなければピッチへ戻します。骨折や靭帯損傷など重症の場合や、軽傷と思われても簡単な動作ができない場合は、すぐにベンチへ交代の必要性を伝達し、ドクターストップとします。その後の対応について、トレーナーだけで判断に困る際は、医学委員会ドクターに電話で相談するなど、いわゆる報告・連絡・相談を行ってください。
今回の講義では、各論として、肩関節脱臼、肩鎖関節脱臼、鎖骨骨折、肘周辺の外傷、手関節部の骨折、骨盤の裂離骨折、膝の靭帯損傷、足関節靭帯損傷、肉離れ、こむら返り、コンパートメント症候群について説明いたしました。内容としては詳しく説明できませんでしたので、各自知識習得いただくことを願います。
・JFAアスレティックトレーナーセミナー研修報告
日時: 平成22年1月8日(金) 11:00 ~ 17:00
場所: 財団法人 日本サッカー協会 4F会議室
テーマ: アスレティックトレーナーの役割
1) 開会挨拶 スポーツ医学委員長 福林 徹 先生
2) JFA ATコンセプトについて JFAU-17日本代表チームアスレティック
トレーナー 山崎 亨先生
3) 現場での救急処置について(AED、RICE処置、擦過傷の処置)
スポーツ医学委員 加藤 晴康 先生
4) ドーピングについて スポーツ医学委員 土肥 美智子 先生
5) コンディショニング(ストレッチング、FIFA11+)
JFAU-17日本代表チームアスレティック
トレーナー 山崎 亨先生
平成21年1月8日、JFAアスレティックトレーナーセミナーが日本サッカー協会にて開催されました。セミナーのテーマは、「アスレティックトレーナーの役割」ということで全国各地のチームに所属しているトレーナーや各県のサッカー協会関係者の方々の参加がありました。
セミナーは上記のような内容で行われ、全体を通して現場で必要となる基礎的な講義内容となっていました。コンディショニングの講義に関しては、FIFAが推奨する傷害予防のためのウォーミングアッププログラムである“The 11+ warm upプログラム”をDVDを見ながら実際に行いました。プログラムの内容としては、ランニングエクササイズ、筋力・プライオメトリクス・バランストレーニングで構成された20分間のプログラムで、それぞれ初級、中級、上級に分けられており、段階的にトレーニングを進めていくというものでした。FIFAの調査ではこのプラグラムを取り入れたチームは有意に傷害発生のリスクが低下したと報告しているとのことです。
今回のセミナーが開催された背景として、JFAでは近年ジュニア期の選手の自分自身のコンディションに対する意識の低下がみられることを挙げており、ジュニアの年代から教育を徹底していくという意向でした。これはFIFAからの要請でもあり、日本だけでなく世界的に若い世代の教育をさらに強化していく動きになっているとのことでした。長崎県は現在Jリーグや日本代表で活躍している選手を多く輩出しています。今後さらに多くの長崎出身の選手をJリーグや世界の舞台に輩出し、長崎県サッカーを盛り上げていくためには県内での若い年代の選手のサポート活動や環境づくりが必要となってくるのではないでしょうか。
(文責 いまむら整形外科医院 理学療法士 吉田 大佑)
・第1回トレーナー講習会(講演要旨):平成21年11月19日
「第64回国民体育大会 少年サッカー トレーナー帯同報告」
講師:持永 至人(医療法人増田整形外科 理学療法士)
【はじめに】
今回、国体少年男子サッカーチームに帯同し、ブロック国体後の強化期間から本国体までトレーナー活動を行った。その活動内容について報告する。
【活動期間・体制】
練習・合宿・試合:8/1(帯同トレーナー1名),8/22(2名),8/29(2名),8/30(2名),
9/5(1名),9/6(1名),9/12(2名),9/13(2名),9/21(2名),9/22(2名)(計10日間)
国体:9/24~9/28(帯同トレーナー1名)(4日間)
【活動内容】
① 選手・スタッフの健康管理
・ 8/22に小無田先生よりアンチドーピングについての講話
・ アンケートの実施(怪我・病気の現病・既往歴、内服薬・サプリメントのチェック)
② 選手の障害・外傷に対するリハビリテーション、応急処置およびコンディショニング
・運動指導、ストレッチ、テーピング、アイシング
③ 飲水・氷・医薬品の準備・管理
④ クールダウン
・ セルフストレッチ・パートナーストレッチ指導
【活動件数】
総対応件数:152件
表1.対応内容
| アイシング | ストレッチ | テーピング | トレーニング | 応急処置 | 合計 | | 58件 | 51件 | 29件 | 4件 | 10件 | 152件 |
表2.対応部位
| 足関節 | 下腿部 | 大腿部 | 腰部 | 股関節 | 足部 | 手関節 | 膝関節 | その他 | | 26件 | 17件 | 16件 | 14件 | 8件 | 5件 | 3件 | 2件 | 2件 |
【経費】
・消耗物品使用金額
・トレーナー交通費
【まとめ】
今回、九州ブロック大会終了後からの帯同ということで、ブロック大会突破の良い流れを壊さないようにチームに早く溶け込めるように努めた。トレーナー体制はブロック国体では1~2名、本国体では1名で対応した。夏場の帯同では脱水対策のため頻回に冷水を準備する必要があり、その他の準備も含めトレーナー1名では選手のコンディション管理に専念することが困難な状況であった。トレーナー増員が望ましいが予算の都合などあり今後検討が必要である。
選手側の問題点として、慢性的な障害を抱える選手が多く、コンディショニングに対する意識が高いとは言い難い状況である。今後は選手の意識を高めるための教育が必要であると考える。
トレーナーも更なる知識・技術を研鑽し選手にフィードバックしていかなければならない。来年も今回の経験を生かし、選手がベストコンディションで大会に臨めるように活動を継続していきたい。
・第88回高等学校サッカー選手権大会県予選抽選会における講演会、実技指導
9月23日(祝)、第88回高等学校サッカー選手権大会長崎県予選の抽選会が日大高校体育館で行われました。これまでは抽選会の後に、Jリーガーや高名な指導者の方にご講演頂いていたそうですが、選手たちが明日から実践できることを聞きたいとの2種の先生方のご意向で、今回よりスポーツ医学委員会が講演と実技を実施することになりました。
選手220~230名、指導者は12~13名と多くの方にご参加頂きました。まずは、『これだけは知っておきたい!~足首捻挫の話~』と題して、コムタ外科整形外科医院(諌早市)の小無田 要先生が30分ほど講演致しました。足首の捻挫はサッカー選手に非常に多くみられ、昨年度の長崎県内の高校生を対象とした調査でもその傾向が見られました。また、捻挫を繰り返し起こしているケースも多く見られています。捻挫を起こした際には、適切な応急処置(RICE処置)→治療→リハビリ→復帰というプロセスが大切ですが、それが正しく行われていないことも、捻挫を繰り返す要因と考えられます。また、捻挫ぐらいと病院を受診しないケースも多いようですが、正しい診断、治療、リハビリを行うことも早期復帰には大切なことです。
その後『応急処置と復帰するためのリハビリテーションと題して理学療法士による実技指導を1時間ほど行いました。捻挫が起こる場面に医療者が居合わせることはほとんどなく、捻挫後のRICE処置は選手・指導者の方々にゆだねられます。
まず、捻挫後に競技復帰するためにはどのようなことができなければいけないか足の機能検査10項目をみんなでやってみました。10点満点を取れた選手は少なかったようです。次に、RICE処置をやってみました。10グループに分かれ、それぞれに理学療法士1名が付き、実際にアイスパック作りや足首に固定する方法などを手順に従って行いました。RICE処置のやり方次第で捻挫の回復過程が決まると言っていいほど重要な処置です。熱心にメモを取る姿もみられ非常に有意義な時間だったように思います。選手・指導者へ正しい方法が浸透し、早期競技復帰に繋がることを私たち医学委員会スタッフは望んでいます。
この活動は、今後も継続していく予定で、来年は『腰痛予防』再来年は『肉離れ』などを予定しています。
長崎県サッカー協会スポーツ医学委員会
(文責 理学療法士 中尾 利恵)
・第8回九州サッカーメディカルミーティング、九州サッカー協会医学委員会
(1) 九州サッカーメディカルミーティング
日時:7月18日(土)6:00pm~7:30pm
場所:ホテル小涌園 会議室
1)高校サッカー選手に対する外傷・障害予防の取り組み 松瀬先生(長崎)
2)メディカルチェックの現場紹介 佐々木先生(大分)3)大分におけるスポーツ外傷・障害予防プロジェクトの概要と九州圏への普及について 大場先生・内田先生(大分)4)ヴィファーレン長崎のメディカルサポートの活動報告 有川先生(長崎)5)足関節捻挫時の内側所見の臨床経過 秋山先生(長崎)
メディカルミーティングには熊本を除く九州各県より約40名のドクター、PTが参加されました。長崎からは、ドクターは西本、秋山、小無田、稲田、今村、PTは有川、持永、松瀬、能、堀、吉田、田辺ほかの各先生が参加しました。
有意義な議論が行われたと思いますが、時間的な制約があり討論が十分でなかった点は反省点でした。大分の先進的な取り組みはいつも参考・目標にさせていただいていますが、長崎の松瀬さんの発表も興味を持っていただきました。学会と違い堅苦しい雰囲気はありませんので、皆様もどしどし応募してください(次は、本年12月福岡、来年8月鹿児島です)
(2)懇親会
メディカルミーティングに引き続き約30名の参加者で懇親会を行いました。各自、親睦が深まったのではないかと思います。
(3)九州サッカー協会スポーツ医学委員会(各県代表者のみ)
日時:7月19日(日)8:00AM~9:00AM
場所:ホテル小涌園 会議室
高槻市での落電事故の判決を受けて賠償責任保険がJFAや各県サッカー協会で検討されています。その中で、ドクターやPTの救急処置に対する訴えがおこった場合にどうするのかという意見も出されています(この件に関しては長崎でも過去に何度か検討したことがあります)。結局、医師に関しては各人が入っている賠償責任保険(医師会、学会など)でカバーされることが保険会社との話し合いで確認されたとのことです。PTの場合も賠償責任保険に入っていれば、それでカバーされるとのことです。
・平成21年度長崎県総合体育大会PTトレーナー活動報告・
| 【人員配置】 | | | | | 6/6(土) | 6/7(日) | | | 北部ふれあい広場 | | 東 | 岩崎 | | 佐世保工業G | | 持永 | 平生 | | 川棚高校G | | 白濱 | 松本 | 星永 | | 鹿町工業G | 松瀬 | 松瀬 | 吉田 | | 佐世保総合G運動広場 | | | | | 小佐々中央多目的A | 持永 | | | | 小佐々中央多目的B | | | |
| (1)試合数 | | 6/6(土) | 8 | | 6/7(日) | 12 | | 全試合数 | 20 |
| (2)人員配置 | | | | | | | | 6/6(土) | | 小佐々多目的 | | | 持永 | | | | 鹿町工業G | | | 松瀬 | | | 6/7(日) | | 北部ふれあい | | | 東 | 岩崎 | | | 佐世保工業G | | | 持永 | 平生 | | | 川棚高校G | | | 白濱 | 松本 | 星永 | | | 鹿町工業G | | | 松瀬 | 吉田 | | | | | | 11名 | |
| (3)総対応件数 | | | | | 総件数 | 実人数 | | 6/6(土) | | 22 | 22 | | 6/7(日) | | 23 | 23 | | 合計 | | 45 | 37 |
| (4)部位別件数 | | | | | | | | | | 顔面 | 肘 | 手首 | 腰 | 股関節 | 太もも | 膝 | 下腿 | 足首 | その他 | | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | | 合計 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 |
・AED講習会
日時:平成21年5月28日
場所:長崎大学医学部良順会館会議室
(1)松瀬PTより過去5年間のメディカルサポート時の傷害報告
救急対応の問題点が指摘された。
(2)スポーツ時の救命救急処置について~AED使用法を主に~
上記の演題で講演が行われた。
スポーツ現場での救急救命処置の実際をスライドで示し、演題終了後人形、AEDトレーナーを使用し実習を行った。(コラム欄に講習会の要旨を掲載致します)
・平成21年度第1回九州サッカー協会スポーツ医学委員会
日時;平成21年4月26日(日)11時~1時30分
場所:福岡市 セントラルホテル福岡
1) 平成20年度活動報告
・トレセン帯同(九州地区でのナショナルトレセン)
U-12,U-14,U-16、JFAアカデミー、スーパー少女プロジェクト
主に大分、熊本で開催
・講義・指導
九州大会開会式等での選手・指導者に対する講義・指導
U-14九州トレセン
九州高校新人大会
2)九州サッカー協会理事会報告
・平成20年度活動報告
・平成21年度活動計画
ナショナルトレセンへの医師帯同
九州協会よりの要望
九州レベルの大会を運営する人のための医事運営に関するマニュアルの作成依頼
スポーツ医学委員会としての案(たたき台)
・大会役員に医事運営委員を入れる(委員は医療関係者もしくは大会関係者)
・スポーツ医学委員長と相談のうえ以下の項目について準備する
1.後方支援病院の確認、連絡
2.救急隊への事前連絡
3.AEDの準備
4.大会には医療関係者(医師、看護師、PTなど)の出動が望ましい
九州協会スポーツ医学委員会およびメディカルミーティング
九州国体開催時
1)メディカルミーティング
7月18日(土)6:00pm~7:30pm
島原市内 ホテル小涌園 会議室
30~40名
演題:3~4題
2)懇親会
7月18日(土)7:30pm~
30~40名
3)スポーツ医学委員会(各県代表者のみ)
7月19日(日)8:00AM~10:00AM
ホテル小涌園 会議室
九州国体
来年より開催時期が8月末へ変更(JFAの意向)されます。
8月20日(金)、21日(土)、22日(日) 鹿児島
・高校生サッカー選手に関する傷害調査報告書
【はじめに】
スポーツ医学委員会は平成16年度より、高校生の3大会(新人戦、高校総体、選手権予選)においてメディカルサポート活動を行ってきましたが、4年間の活動を通して、身体に何らかの障害をもつ選手が多いことが分かりました。そこで、選手の外傷・障害の発生状況を把握し障害の予防に努める必要があると考え、高校生の選手を対象に外傷・障害調査を実施しましたので、その調査結果を報告致します。
【調査の概要】
1. 調査期間 :平成20年4月~6月末日
2. 対象 :長崎県サッカー協会第2種登録チーム
男子61校2137名、女子3校64名、計64校2193名(平成20年4月現在)
3 有効回答数(回答率):
|
男子
|
42校(68.9%)
|
1480名(69.3%)
|
|
女子
|
3校(100%)
|
54名(96.4%)
|
|
合計
|
45校(70.3%)
|
1534名(69.9%)
|
|
高1
|
高2
|
高3
|
その他
|
|
538名
|
502名
|
487名
|
7名
|
【調査結果】
Ⅰ.選手からの回答
1. 身長・体重について
平均身長 169.4±6.0cm(149~190cm) 平均体重 59.6±7.8kg(39~114kg)
2. ポジションについて
|
GK
|
119名
|
|
DF
|
483名
|
|
MF
|
527名
|
|
FW
|
293名
|
|
複数回答
|
79名
|
|
無回答
|
33名
|
3. 利き足について
利き足 右88.2% 左11.8%
4. サッカーの開始年齢について
サッカーを開始した年齢は、平均は10.3±2.9歳(3~17歳)で小学2~4年生が最も多かった。また、全体の73.2%の選手が小学生の時期にサッカーを始めていた。
5 サッカー以外のスポーツ歴について
サッカー以外のスポーツ歴の有無については、「ある」と答えた選手は808名(52.7%)、「ない」と答えた選手は726名(47.3%)であった。「ある」と回答した選手の競技種目及びその人数は下記に示す。
|
水泳
|
383名
|
|
ソフトボール
|
104名
|
|
野球
|
98名
|
|
陸上
|
78名
|
|
バレーボール
|
61名
|
| バスケットボール |
56名
|
|
空手
|
49名
|
|
剣道
|
46名
|
|
相撲
|
42名
|
|
テニス
|
35名
|
|
卓球
|
25名
|
|
柔道
|
18名
|
|
体操
|
13名
|
|
バトミントン
|
12名
|
|
その他
|
53名
|
|
|
|
|
|
|
「ある」と答えた選手は238名(15.5%)、「ない」と答えた選手は1296名(84.5%)であった。最も多かったのは喘息120名であった。
7. 小・中学生当時の練習日数・時間及び現在の練習日数・時間について
|
|
練習日数(1週間平均)
|
練習時間(1日平均)
|
|
小学
|
4.4±1.4日
|
2.4±0.7時間
|
|
中学
|
6.0±1.2日
|
2.6±0.6時間
|
|
高校
|
6.5±0.9日
|
2.7±0.6時間
|
8. 睡眠時間・食事の摂取状況について
睡眠時間 1日平均 6.5±0.6時間(3-10時間)
食事摂取
|
|
朝食
|
昼食
|
夕食
|
補食
|
|
はい
|
1463名(95.4%)
|
1529名(99.7%)
|
1530名(99.7%)
|
699名(45.6%)
|
|
いいえ
|
69名(4.5%)
|
3名(0.2%)
|
2名(0.1%)
|
831名(54.2%)
|
|
無回答
|
2名(0.1%)
|
2名(0.1%)
|
2名(0.1%)
|
4名(0.3%)
|
〈補食の頻度に関して〉
1日平均 1.67±0.91回(1~5回)
9. 「これまでに1週間以上練習または試合を休む必要があった傷害」に関して
1)傷害の有無について
過去の傷害の有無に関して「ある」と答えた選手は902人(59%)、「ない」が617人(40%)、と、全体の6割の選手が何らかの傷害で練習・試合休止の経験をしていた。延べ件数は2,321件で、1人平均2.92±2.35回(1~18回)受傷していた。
「ある」と答えた選手の受傷回数を下記に示す。
|
1回
|
337名
|
|
2回
|
225名
|
|
3回
|
139名
|
|
4回
|
74名
|
|
5回
|
46名
|
|
6回
|
38名
|
|
7回
|
17名
|
|
8回
|
9名
|
|
9回
|
8名
|
|
10回以上
|
8名
|
2)受傷時期について
平均受傷年齢は14.9±2.5歳で、中学2年生の受傷が最も多く、次いで高校1年生、高校2年生多かった。
3)受傷部位について
|
上肢
|
350件(15%)
|
|
体幹
|
279件(12%)
|
|
下肢
|
1627件(70%)
|
|
その他
|
65件( 3%)
|
4)受傷した疾患について
最も多かったのは足関節捻挫451件、次いで手・手指骨折191件、オスグッド病130件、腰椎分離症106件、足関節骨折92件であった。そのうち、今現在、練習・試合時に問題があると回答があったのは2,321件中421件(18.1%)であった。
「現在もケガの影響が残っているもの」は、膝複合靭帯損傷75%、次いで腰椎椎間板ヘルニア48%、膝前十字靭帯損傷46.2%、膝半月板損傷44.4%、腰椎分離症44.3%で、腰部・膝関節に問題を抱える選手が多いことが分かった。
5)高校生年代で受傷率が高い疾患について
高校生年代で受傷率が高い疾患は下記に示す通りである。前項で述べた、「現在もケガの影響が残っているもの」が多い、膝複合靭帯損傷・膝前十字靭帯損傷・膝半月板損傷、腰椎椎間板ヘルニア・腰椎分離症の発生率も高くなっている。
|
疾患名
|
件数
|
%
|
疾患名
|
件数
|
%
|
|
膝複合靭帯損傷
|
4件
|
100%
|
膝半月板損傷
|
18件
|
50.0%
|
|
シンスプリント
|
36件
|
81.8%
|
ジャンパー膝
|
3件
|
50.0%
|
|
太ももおもて 打撲
|
13件
|
76.5%
|
腰 その他の疾患
|
47件
|
47.5%
|
|
すね 疲労骨折
|
12件
|
70.6%
|
足関節捻挫
|
199件
|
44.1%
|
|
膝内側側副靭帯損傷
|
20件
|
69.0%
|
太ももおもて 肉離れ
|
36件
|
42.4%
|
|
肩脱臼
|
5件
|
62.5%
|
膝 その他の疾患
|
45件
|
41.3%
|
|
膝前十字靭帯損傷
|
16件
|
61.5%
|
腰椎分離症
|
43件
|
40.6%
|
|
腰部捻挫
|
9件
|
52.9%
|
腰椎椎間板ヘルニア
|
19件
|
38.0%
|
(%は現在もケガの影響が残っているものの割合)
Ⅱ.チームからの回答
1. チーム構成・選手数について
|
|
平均人数
|
|
監督
|
1.0±0.2名(1~2名)
|
|
コーチ
|
0.8±1.1名(0~5名)
|
|
マネージャー
|
1.4±1.9名(0~6名)
|
|
ドクター
|
0名
|
|
トレーナー
|
0.1±0.5(0~2)名
|
|
その他
|
0.4±0.7(0~2)名
|
|
|
チームの平均
|
|
1年生
|
13.7±9.3名(1~50名)
|
|
2年生
|
12.6±7.6名(1~6名)
|
|
3年生
|
12.6±8.6名(0~35名)
|
|
全体
|
38.9±23.1名(8~110名)
|
2. 練習日数・練習時間について
1週間の練習日数 :平均 6.1±1.0日(2~7日)
平日の練習時間 :平均 2.2±0.4時間(1~3時間)
休日の練習時間 試合がない日:平均 3.1±1.0時間(0~5時間)
試合がある日:平均 5.3±1.9時間(0~8時間)
3. 年間の試合数について
公式戦:平均14.7±9.2試合(1~40試合) 練習試合:平均48.5±35.6試合(2~120試合)
4. ウォーミングアップに関して ※複数回答あり
(1)平日 (2)休日 (3)試合時
|
チーム全体で実施
|
36チーム
|
|
個人で実施
|
7チーム
|
|
行っていない
|
2チーム
|
|
その他
|
0チーム
|
|
チーム全体で実施
|
35チーム
|
|
個人で実施
|
8チーム
|
|
行っていない
|
2チーム
|
|
その他
|
1チーム
|
|
チーム全体で実施
|
38チーム
|
|
個人で実施
|
6チーム
|
|
行っていない
|
0チーム
|
|
不明
|
1チーム
|
(4)ウォーミングアップの内容
|
ランニング
|
28チーム
|
|
ストレッチ
|
35チーム
|
|
ブラジル体操
|
16チーム
|
|
基礎練習
|
32チーム
|
|
その他
|
5チーム
|
5. クーリングダウンに関して ※複数回答あり
(1)平日 (2)休日 (3)試合時
|
チーム全体で実施
|
30チーム
|
|
個人で実施
|
12チーム
|
|
行っていない
|
3チーム
|
|
その他
|
0チーム
|
|
チーム全体で実施
|
33チーム
|
|
個人で実施
|
10チーム
|
|
行っていない
|
2チーム
|
|
その他
|
0チーム
|
|
チーム全体で実施
|
31チーム
|
|
個人で実施
|
12チーム
|
|
行っていない
|
2チーム
|
|
その他
|
0チーム
|
(4)クーリングダウンの内容
|
ランニング
|
25チーム
|
|
ストレッチ
|
35チーム
|
|
その他
|
1チーム
|
6. 傷害の記録について
1年間を通して、チーム・選手の傷害を記録しているのは10チーム(25.6%)、記録していないチームは29チーム(74.4%)であった。
7. 昨年1年間で手術を受けた選手数について ※複数回答あり
|
肩関節
|
手関節
|
腰
|
膝関節
|
足関節
|
足部
|
その他
|
|
2名
|
4名
|
2名
|
13名
|
10名
|
14名
|
1名
|
昨年1年間で手術を受けた選手は33名であった。最も多かったのは足部14名、次いで膝関節13名、足関節10名であった。
【まとめ】
今回の調査結果より、約60%の選手が過去に1週間以上の練習・試合を休止するという重大な障害を経験していることが分かった。また、サッカーの競技特性上、足関節・膝関節を中心とした下肢に傷害を経験している選手が多く、その好発学年は中学2年生、高校1年生、高校2年生であった。さらに、「現在もケガの影響が残っている」ケースが多い疾患は、膝関節の靭帯損傷・半月板損傷や腰椎椎間板ヘルニア、腰椎分離症などの腰部・膝関節の疾患であるが、それらの発生件数及び発生率とも高校生年代で高くなっていた。
体力や技術などの競技力の面ばかりでなく、スポーツ傷害の面からも高校1年生入学時点での身体能力、活動レベルが問題となる。したがって、中学3年生が中総体、宅島杯終了後の高校入学までの約6か月の受験期をどのように過ごすかが大きな課題と考えられる。
・平成21年度長崎県サッカー協会スポーツ医学委員会定例会 議事録
日時: 平成21年1月21日 7:00pm~ 8:30pm
場所: エキサイ会病院7F会議室
議事
1) 九州サッカー協会スポーツ医学委員会
九州サッカーメディカルミーティングの報告(別紙資料配布) (担当:今村)
2) 長崎県内開催の九州大会への会場医派遣に伴うメディカルスタッフの充実・組織(担当:松瀬)
・ サッカー協会医学委員会に所属する、医師、看護師、理学療法士を派遣する
・ 大会主催者よりサッカー協会事務局を通じて派遣の要請を受ける
※県内の高校3大会については従来通りの形で派遣する
3) 九州国体開催時(7月18日(土)夜、島原市)
・ 九州サッカー協会スポーツ医学委員会(5:00~6:00)
・ 九州サッカーメディカルミーティング(6:00~7:30)及び懇親会
(担当:松瀬、今村)
・演題については以下のものを予定していきたい
1. 高校サッカー選手の外傷予防活動(今後活動内容について高校の指導者とも協議し、具体化に向けて検討していく)
2. V・ファレーン長崎のメディカルサポート報告
3. 三菱重工長崎のメディカルサポート報告
4) 2009年度事業計画/予算案(担当:西本)
5) V・ファレーレン長崎の支援態勢(担当:秋山):別紙資料配布
・ JFLではチームドクターの帯同は必要ないが、ホームゲームにおけるゲームドクターは必須
・ 体制:秋山先生をチーフとして複数のドクターがサポートしていくことが確認された
6) その他
メーリングリスト、ホームページの件
・平成20年度第1回長崎県サッカー協会スポーツ医学委員会定例会 議事録
平成20年1月18日(金) 19:00~21:00ホテルサンールト長崎
議題:
報告事項 : 第5回九州サッカーメディカルミーティングの報告
協議事項 : 平成20年度の活動方針
1)大会出動(医師、理学療法士)
直前に出動の依頼がある点については協会事務局、各種委員会に
対して再度、申し入れを行う。
2)トレセンにおけるメディカルチェック
ナショナルトレセン(九州地区)におけるメディカルチェックの問題点
・時間的制約
・故障者が参加する場合がある
→各県における事前のメディカルチェックが必要である
長崎県におけるトレセン活動(長門技術委員長よりの話)
県トレセン(U-12)
1回/月(土曜日) 約30名 開催地は県下(長崎、島原など)4地区マッチデー:
1回/月(土曜日) 16名×4=64名
県トレセン(U-15,16)
1回/月(土曜日) 約30名 開催地は県下(長崎、島原など)
11月もしくは12月のトレセンの際にメディカルチェックを行う。
また、事前のアンケート調査も実施
今村が長門委員長と打ち合わせを行う。
3)講演会、講習会
ストレッチ講習会の報告
現在まで以下の3地区で開催
大瀬戸(バスケット、ソフトなど)
長与(サッカー)
大瀬戸(サッカー)
H20.2.23 大串(西海市)にてストレッチ講習会を予定
4)C,D級講習会の講師
開催地区のDrが担当することが望ましい。
5)ホームページ
①ホームページの内容
第1回のコラム担当は西本先生
②委員会メンバーの名簿の作成
6)高校サッカー活動報告
松瀬PTより高校3大会のメディカルサポートについて報告された
→アンケート調査の実施
(高校生世代;外傷調査 全校、全選手対象に)
調査は3学年が揃う4~5月ごろ
7)Vファーレンの活動内容
今回Vファーレンにてメディカルサポートをおこなっている3名のPTが参加された。
本定例会を年数回開催することが確認され懇親会へ移った。
報告:今村
・第5回九州サッカーメディカルミーティング
平成19年12月1日(土) 福岡市 パピヨン24ガスホール
参加者:沖縄、鹿児島を除く九州6県の医師、理学療法士など約40名。
演題:
「サガン鳥栖の2006年~2007年 の症例報告」 藤先生(百武整形外科)
「ロッソ熊本のメディカルチェックにおける血液検査の検討」小川先生
「そけい部痛症候群、下腿コンパートメント症候群の症例報告」
秋山先生(貞松整形外科)
「大分県サッカートレセン・トレーナーサポート報告」 中西先生(大場整形外科)
協議事項:九州サッカー協会医事委員会の件。
九州サッカー協会内に医事委員会を来年度に立ち上げる。
委員は九州8県のスポーツ医科学委員会の委員長が務める。
委員長は中島先生(福岡)に決定。
大場先生(大分)はすでに九州協会の常任理事。
副委員長は今後、協議予定。
医事委員会の目的は
「九州におけるサッカーにたいするメディカルサポートの質の向上と均一化を図る」ことであり、トップアスリートと一般の選手、小、中、高校生に対するサポート活動の2本柱で活動していくことが確認された。
具体的な活動内容については今後の委員会の中で詰めていく。
委員会の開催は年3回
1)各県持ち回り、2)九州理事会開催時に福岡、3)九州サッカーメディカルミーティング開催時の12月上旬に福岡
報告: 今村
このページのトップに戻る
|